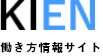「マナー」について #4
河原一久
著書に『読む寿司』(文芸春秋)、『スター・ウォーズ論』(NHK出版)、『スター・ウォーズ・レジェンド』(扶桑社)など。
監訳に『ザ・ゴッドファーザー』(ソニーマガジンズ)。
財団法人通信文化協会『通信文化』に食に関するエッセイ「千夜一夜食べ物語」を連載中。
日本ペンクラブ 会員。
大抵の場合、この是非論では「ワサビは醤油に溶かすのではなくネタの上に載せて食べる」という意見と、「ワサビは醤油に溶かした方が辛さを抑えられるので溶かす」という意見がまず紹介される。その上で「寿司職人に聞いたワサビの使い方」というものが披露される。
曰く、「ワサビは香りが大切ですので、醤油に溶かずにネタの上に載せて味わって欲しい」というものだ。
これはまったくその通りの意見なのだが、これって実は「本ワサビ」を前提に語られているものであって、手頃な回転寿司や居酒屋などで使われる「粉ワサビ」や「練りワサビ」のことではない。
「本ワサビ」はおろしてから数分くらいしか香りが保てないものだ。
だから寿司職人はしょっちゅうワサビをおろしている。
こうした「香りが大切」と呼べるほどの本ワサビはそれ自体が高級品だ。
「香りを味わって欲しい」というコメントも「最高の味を楽しんでほしい」という気持ちからのものだ。
しかしだ・・・
現在の日本人の8割前後が「寿司」イコール「回転寿司」として親しんでいる。
だから大衆のほとんどはこうした手頃なお店での「ワサビの使い方」という感覚になっているし、そもそもワサビが「ワサビ醤油」という使われ方をするのも、こうした店でのことがほとんどだ。
「練りワサビ」や「粉ワサビ」などは「西洋ワサビ」と呼ばれるホースラディッシュを加工して色をつけ「ワサビのように見える」ようにした代用品だ。
「香り」はほとんど感じられず、「辛み」が主体の調味料だ。
だから醤油に溶かすことで辛みの調節ができるし、海鮮丼などの場合には、「ワサビ醤油」を上からかけ回して使う方法もある。
この場合、出されたワサビが「本ワサビ」ならばネタの上にワサビを載せて香りも楽しめばいい。
粉ワサビなどなら「ワサビ醤油」でも構わないし、そもそも練りワサビメーカー自体が「醤油溶けしやすいワサビ」の開発をしてきているのである。